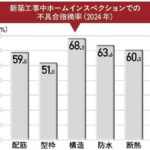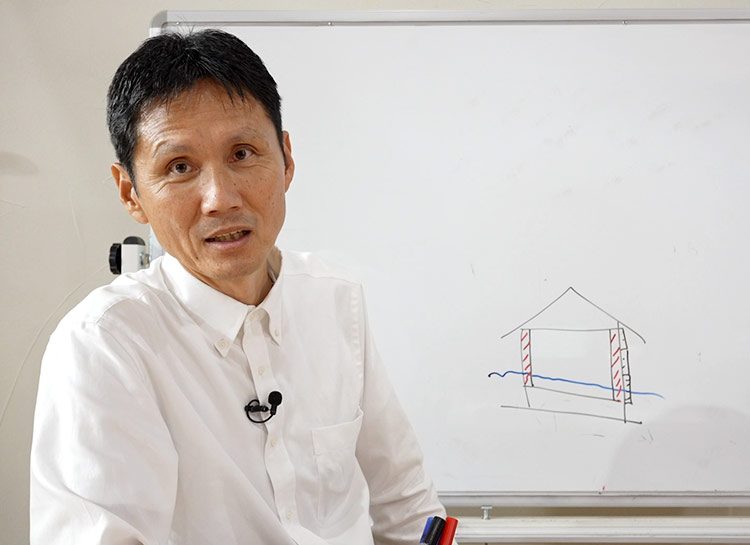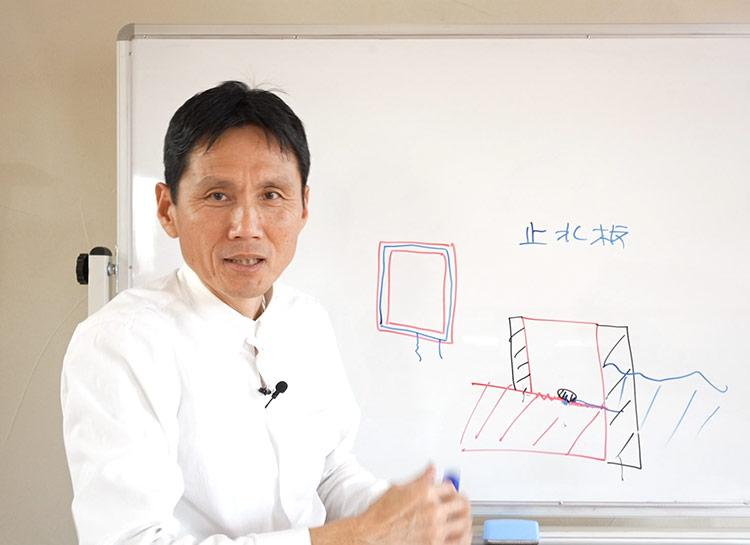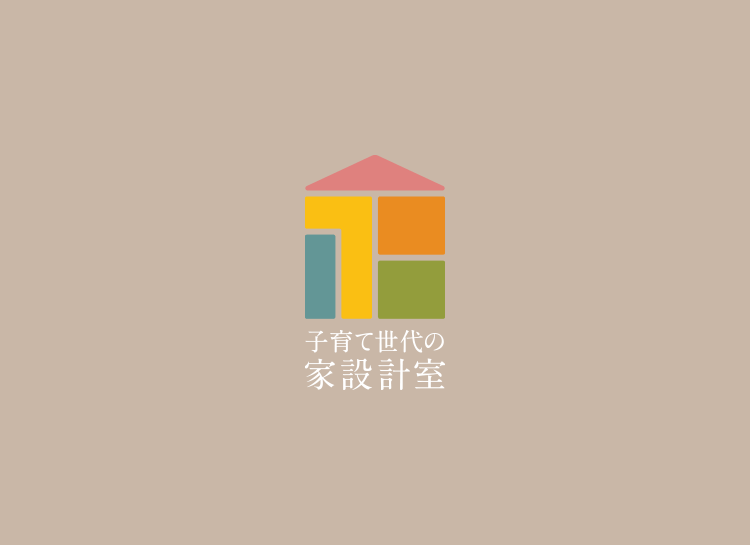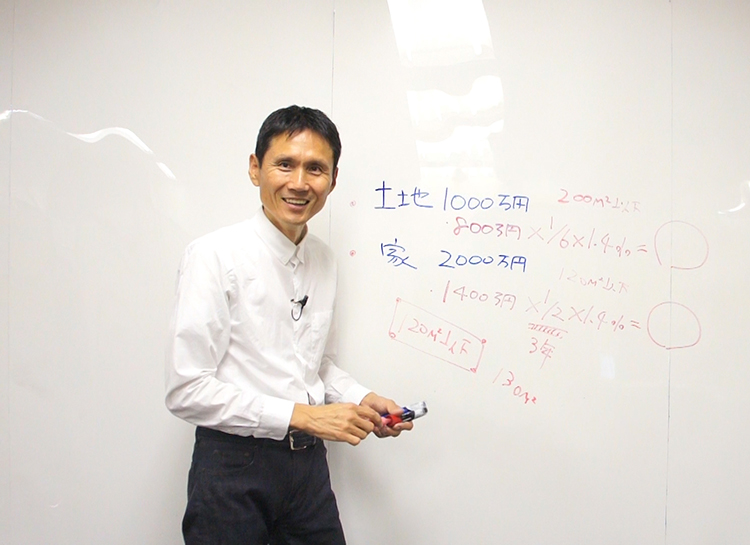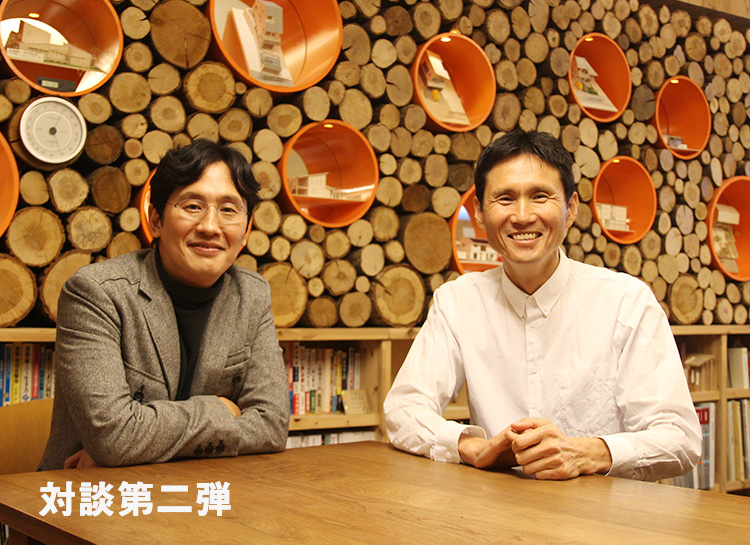今回は、私が配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。
まず最初のコメントです。以下の動画に対していただきました。
◼︎①下田島モデルハウス見学にお越しになるお客様へのお願い②ペロブスカイトの使い道を考えてみた③屋根裏エアコン1台にこだわる必要はない④役所に建築確認申請書を出したら嫌な顔をされた⑤南西の南東、どちらの向きが良いのか?⑥空き家は活用できるか?
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/model_house_onegai/
「今回の動画にありました日射についてですが、まさに私が建築予定の土地が南西寄りに向いており、日射シミュレーション上では西日のため軒での吹き抜け部分のカバーは厳しく、1階部分はシェードでカバーするという状況です。平屋でスキップフロアがあるため、天井まで5〜6mほど高さがあります。ここで、1つ質問です。外壁を黒にしたいと考えていたのですが、やはりこのような状況では、夏型結露のリスクを考慮して、白は好みでないためグレーで妥協するべきでしょうか?それとも夏型結露のリスクのみであれば、可変透湿シートを施工すれば黒でも大丈夫なのでしょうか?ご回答いただけたらと思います。ちなみに6地域で、結露計算上、夏と冬はリスクがないため、気密シート自体の施工もありませんが、黒系だと表面温度の上昇での結露リスクが気になっています。」
夏型結露に関しては、他の動画でも私なりの意見や考えを述べさせていただいていますが、外壁の色が黒だから夏型結露をするとか、外壁を黒にしなければ夏型結露はしないということはないと思います。断熱材がないような家の中をガンガン冷やしたら起こるかもしれませんが、外壁の色だけで断熱材の中が熱くなるかどうかというと、よくわかりません。
外壁というのは、通気を取って熱を逃がした上で、中に断熱材をしっかりと入れて、気密シートを貼るのが原則です。夏は壁よりも頭の方が暑くなることがあるので、それを考えたら、仮に外壁がグレーでも頭が黒だったら、そっちが結露するような感じも無きにしも非ずな気がします。天井断熱だったら話は別ですが、屋根断熱の場合は結露が起こるリスクがあるかもしれません。
ちなみに当社では、ライトブラックという色を使っています。ダークブラックは使いません。暑さの問題というよりも、傷や劣化が目立つし、汚れや埃もつきやすいためです。ブラックの車と同じで、劣化や汚れの問題を踏まえると、綺麗には保てないんじゃないかなという気がします。それだったら1段下のライトブラックにした方がいいんじゃないかと思います。夏型結露を回避したいのであれば、外壁の色を考えるよりも、ちゃんと通気を取ることや、ちゃんと断熱材を入れることが重要です。
可変気密シートを施工すれば夏型結露のリスクを減らせるのかということですが、その可能性は高いです。可変気密シートは当社も使っていますが、作動するのはよっぽどの状況なので、スイスイと湿気が出るようなものではありません。ただ、通気をちゃんとするということになると、気密シートを室内側に貼って、こちら側の抵抗を高めて、向こうに抜けやすくすることが原則です。
質問者さんの場合、気密シート自体の施工はないとのことですが、プラスチック系の断熱材を使うことで役割を兼ねてしまうということなのかもしれません。詳細はわかりませんが、私なりに考えるとそんな感じです。
下田島モデルハウスの周りに、まだ建てて3〜4年ぐらいなのに、北側の外壁がすごく汚れているお家があります。断熱材が入っているんだろうなというところがグリーンになっているわけです。これは冬型外壁結露が原因なんですが、外壁がそういう風になっているということは、住んでいる方はかなり寒い状況だと思うし、燃費もよくないような感じがします。
たった3〜4年でそうなってしまう家が、30年持つかどうかというと、「うーん?」と思ってしまいます。表面の汚れは落として塗装すれば綺麗になりますが、結局は同じことを繰り返すことになるわけです。見えないところが劣化していく感じになるので、そういう意味で言うと、家については「不味い店に行ってみるか!」という感じで、ふざけて考えるのはダメだなと思います。
ましてやそういう家に住んでいるのは、若い方が多いじゃないですか。お子さんもまだ小さくて、下手すると50年ぐらい住むことになるかもしれないけど、さすがに50年は無理かなという感じがしてしまいます。でも住んでいる方は、そういうのをわかって買っているわけじゃないと思うし、東京の大きな建売メーカーさんも悪気があってやっているわけじゃないと思います。
情報を知っている方と知らない方の差というのは、これだけ出てしまうんだなと思います。住宅業界は情弱ビジネスだとよく言われますが、その差は本当に大きいと思います。
次も、先ほどと同じ動画に対するコメントです。
「私の家は西日がよく当たる南西角地にあります。このような西側壁でペロブスカイト太陽光発電を行うと、夕方の電力消費が多い時間帯に効率的な発電ができると思っています。特に、将来は市場連動型の料金体系で、夕方の電気料金が上がる可能性がありますので、有効だと期待しています。また、壁掛け型は大掛かりな足場なしに交換できそうな気がしますので、耐用年数が低いデメリットを多少補えるかもしれません。」
ペロブスカイトは薄いフィルムみたいな感じで軽いので、太陽光みたいに架台を組んだり、ネジで固定したりせずにできるからいいんじゃないかということですが、デメリットとして、耐用年数が10年程度だったり、発電効率が太陽光の半分以下ぐらいということがあります。軽くてどこでもできるというメリットもあるかもしれませんが、きちんと固定するのは案外大変です。
硬い面のあるものを固定するとなったら、それ自体に剛性があるので、4つ角にビスを打てばいいですが、ペロブスカイトをきちんと壁面につけるとなると、フレーム枠の中の桟か何かに対してペタッと貼らなければならないと思います。群馬県の赤城山の麓だったら、飛んでいってしまう可能性もあります。架台をつけて、ピンセットを使って窓から下げておけば、天気のいい日は発電すると思いますが、「今日は風が吹くから外そう。」というのはなかなか現実的じゃないですよね。
ペロブスカイトのいいところは、キャンプの時にフィルムをボンネットにポンと広げられるところとか、屋根のルーフに簡易的に両面テープか何かを貼って、危なかったらペリペリと剥がせるところだと思いますが、家の外壁面はペリペリ剥がせないので、意外に大変なんじゃないかと思います。この辺りは、みなさん楽観的に考えているのかもしれませんが、そんなに簡単なものではない気がします。
そもそも、屋根がないようなビルの壁面に貼りつけたり、車の屋根に貼りつけたりするものなので、その方法じゃなければ発電しないような、円筒形で屋根がないビルや、真四角で屋根がないビルについては、お金をかけて全面に貼ってあげて、発電するようなタワーにしてもいいと思います。個人の使用であれば、車の屋根に貼るとか、ベランダに置くという感じなので、すごい量を壁面に貼るということは想定されていないと思います。いっぱい貼れば配線もどんどん増えるし、線の取りまとめも大変そうですよね。その辺はまだ勉強不足なので、ご存知の方がいたらコメントで教えてください。
次は、以下の動画に対するコメントです。
◼︎地盤が良いのに地盤補強を勧める理由
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/jiban_hokyou_riyu/
「おそらく、地盤の支持力はあるけど、土質採取して、砂かつ水位があり、液状化計算をした結果として、補強工事の判断をしたと思われます。大手ハウスメーカーは型式取得していますので、地盤説明書の提出義務があり、液状化の検討を行っています。」
もしかしたらこの方は、大手ハウスメーカーさんで家を建てた人なのかなとか、関係者の方なのかなと思いました。地盤調査の際に、土を採取して液状化計算をするというのは、基本的にはみんなやることです。別に大手ハウスメーカーさんだからやっているというわけではありません。そういうのも含めた上で地盤補強の有無を判断するべきなので、ちょっと解せないかなという感じがしてしまいました。
ハウスメーカーさんはすごいことをやっていると思う方もいるかもしれませんが、地盤調査の方法はみんな同じだし、地盤調査に関しても、結局はハウスメーカーさんの下請けさんがやっています。地盤調査から地盤補強まで自分の会社で全部やっていたら大変だし、そこまでのコストはかけられません。やっぱり餅は餅屋で、専門の会社に任せるのが一番です。
ハウスメーカーさんはいっぱい家を作っていますが、窓についてはYKKさんとLIXILさんの2社に分けて作ってもらっているのが現状です。また、縦滑り出し窓はYKK、引き違い窓はLIXILみたいな感じで、リスク管理をしているのも事実です。自社で作っているものも一部ありますが、窓でも何でも全てを自分で作っていたら割に合いません。
次は、以下の動画に対するコメントです。
◼︎①お客さんのお家の年間電力消費量②遮熱型ハニカムシェードを付けるときの注意点③計画通りにいかなくても良いこともある④床ガラリからコンクリートのニオイが漏れる⑤空調計画はイマジネーションといい加減さ!?
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/denryoku_keikaku_image/
「2年経過しましたが、エアコンに付着したダストが少なく、クロスフローファンも綺麗でした。室内側の相対湿度管理とダスト対策がしっかりできているとカビが生えにくいなと思います。結露満載の頃の家は速攻でカビが生えていましたから。」
カビが生えるかどうかというのは、家の中が寒いかどうかによります。寒い家は乾燥することで、結局カビが生えやすくなります。お医者さんが「湿度を60%にしないと風邪をひく。」と言うのでどんどん加湿するわけですが、その水分によってカビが生えることもあります。
快適な家を作れば、埃が家の中に入りにくくなります。そうすると、エアコンにダストがつきにくくなって、カビが生えなくなるというように連鎖していきます。ちゃんとした家を作れば、細かいことは気にならなくなるというのが結論です。