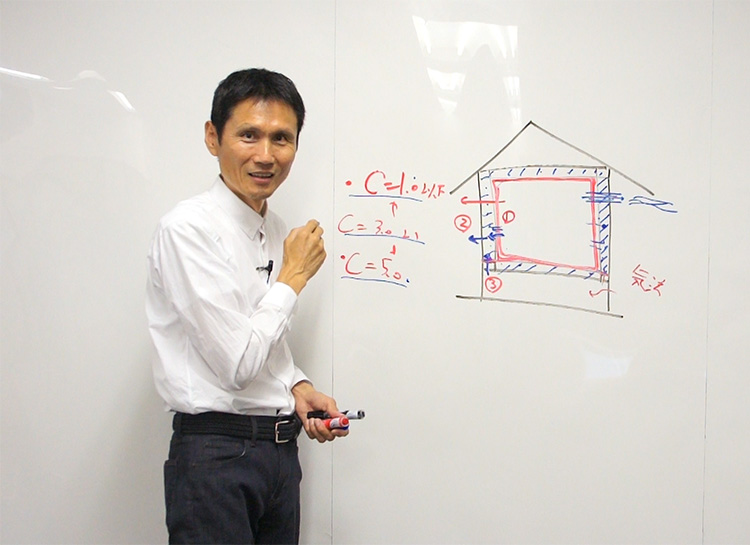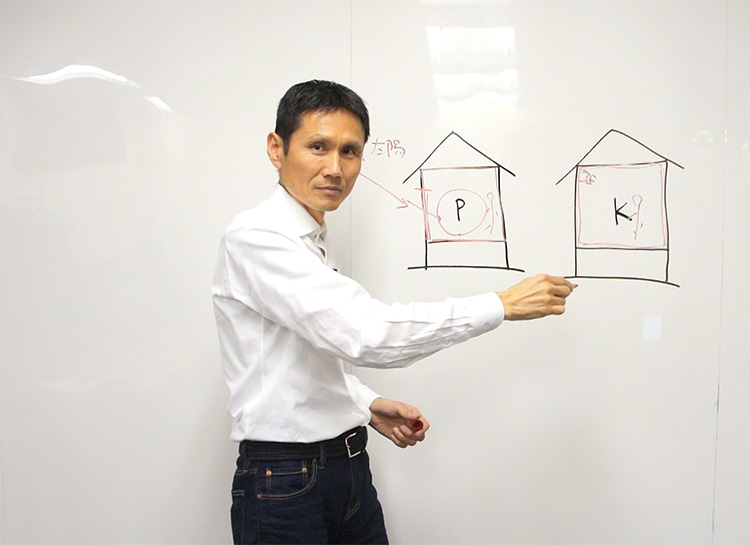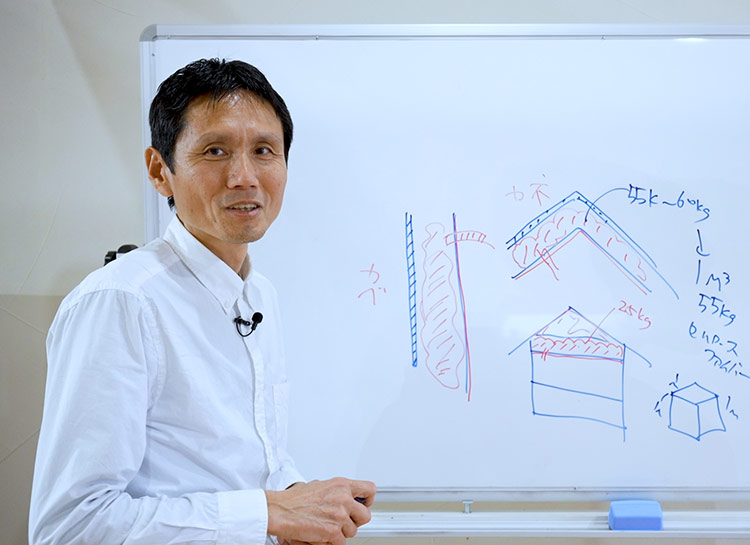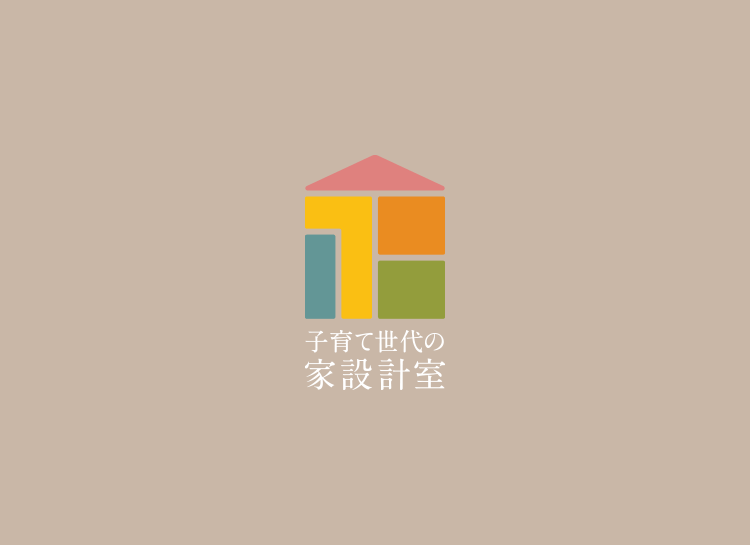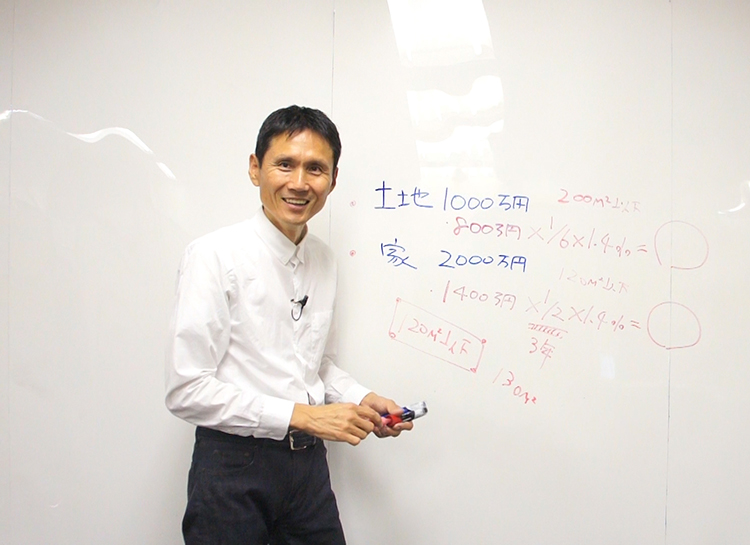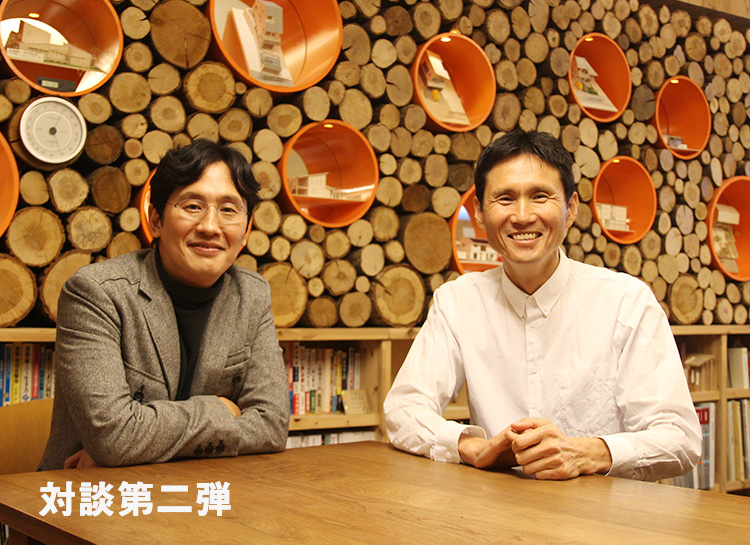今回は、私の配信したYouTubeに対するコメントをご紹介します。
まず最初のコメントです。以下の動画に対していただきました。
◼︎①下田島モデルハウス見学にお越しになるお客様へのお願い②ペロブスカイトの使い道を考えてみた③屋根裏エアコン1台にこだわる必要はない④役所に建築確認申請書を出したら嫌な顔をされた⑤南西の南東、どちらの向きが良いのか?⑥空き家は活用できるか?
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/model_house_onegai/
「今回メルマガの感想をYouTubeで取り上げていただき、ありがとうございました。動画の中でおっしゃっていたので、一応お答えしておきます。21年前の外断熱ブームの時の家ですが、蓄熱暖房機を10.9kW使用していました。電気代の高騰で代わりの暖房設備を検討していたところ、人柱覚悟で床下エアコンにチャレンジした次第です。もともと基礎断熱で床下空間と壁内を通気させる工法だったので、できるはずと考えました。お世話になっている工務店さんは2年前から床下エアコンを施工しているとのことでした。もちろん後付けなので、全て自己責任で事前の情報収集は綿密に行いました。森下さんにも質問させていただきました。結果としては、85〜90点くらいはつけられるのではないかと思っています。ランニングコストはG2以上の家の方より高額だと思いますが、蓄熱暖房機の時の電力使用量よりは最大半減しています。先日の最強寒波来襲の際に、床下サーキュレーターの配置を毎日微調整して、一番寒かった勝手口と脱衣所も室温22〜23℃で終日安定しました。お風呂の床も何だか暖かくなりました。21年前の家でもここまでできましたよ。」
実を言うと、蓄熱暖房機は私の家にもついていました。15年前に2回目の家を作った当時は、蓄熱暖房機ブームでした。大きな箱の中に蓄熱用のレンガが入っていて、それを深夜電力を使って暖めて、ファンで緩やかにファーッと送り出すことで家の中を暖めるシステムです。深夜電力は安かったですし、つけると本当に暖かかったので、当社のお客さんにも勧めていました。
ただ、今考えると、蓄熱暖房機というのはレンガが蓄えた熱を穏やかに放出するぐらいの勢いしかないわけです。エアコンみたいにバンバンと熱を送るわけじゃなくて、石焼き芋の石をいっぱい並べて、その熱を扇風機でフワーッとやるみたいなものなわけです。蓄えられる熱も限られるし、そんなにすごい勢いで遠くまで届けられるわけじゃないので、結局は家の断熱・気密性能が高くなければどんどんロスしていくことになります。
あの頃は断熱・気密というものにそこまで意識がない時代でしたが、断熱・気密をちゃんとして、パッシブ設計に沿った窓のつけ方をした上で使えば、さらに良いでしょうね。でも、今蓄熱暖房機を使うとなると、電気代がとんでもないことになってしまうと思います。
このことから言えるのは、基本となる家をちゃんと作っていただけているからこうなったということです。基本的な家の性能をちゃんとしておけば、環境が変化しても何とか対応できるからです。基本的な家の性能というのは、パッシブ設計の原則に沿って、建てる場所に応じた家の間取りにすることや、なるべく室内の空気を回しやすい間取りにすることです。こういうところをちゃんとやっていけば、どこかのタイミングで地球が寒冷化しても、機械でコントロールすることができます。また、気温がちゃんとしていれば、すごく送風するような機械を使わなくても、機械を1個増やすだけでコントロールできます。
基本的な性能というとUA値の話になりがちですが、断熱・気密性能、窓の配置、間取り、室内の空気の流れ、光の入り方というところをしっかりしておけば、快適になりやすいです。なおかつ、メンテナンスコストのかかりづらい家にするということを同時にやっていくことが重要です。電気代は削減できても、メンテナンスコストで一気に取り返される場合があるからです。この辺りは気を付けた方がいいのかなと思います。いずれにしても良かったです。
次も、先ほどと同じ動画に対するコメントです。
「①のテーマ“下田島モデルハウス見学にお越しになるお客様へのお願い”ですが、自分が過去に行ってすごく不味い料理を出すお店の話を知人にすると、“そんなに不味いならぜひ食べて見たいから、連れて行ってくれ”と言われることが時々あります。“ものすごく不味くて後悔するから、考え直したら?”と諭すのですが、怖いもの見たさがある人というのは、自分が思う以上にたくさんいるみたいです。不味いお店なら数千円の損害と一時の不幸で済むからいいですが、住宅選びは失敗すると一生不自由な生活に耐えなければいけなくなる故に、真剣に向き合うべきテーマだと思います。また、話は逸れてしまいますが、群馬県はグルメがかなり充実していて個人的には大好きです。なぜ都道府県ランキングでは、毎年群馬県は不人気なんだろう?と思っています。」
モデルハウスにお越しになる方はお客さんなので、当然メリットはなくちゃいけませんが、私の方にもメリットがないとビジネスとして成立しません。民間の商売であって、別に税金でやっているわけではないし、お互いにメリットがなければ長続きもしないと思います。
せっかくお時間を使ってモデルハウスに来られるのであれば、事前に当社がどういう家を作っているのか、金額はどのくらいするのかというところを見てもらって、気に入っていただけるか、興味があるかどうかをまずチェックしてほしいです。それも何もなしに「変わった家だからちょっと行ってみようか。」という感じで来られて、そもそもそんなに予算をかけたくないとか、何で外壁に木を張っているんだろうと思われてしまうのは非常に残念です。お客さんのせっかくの時間を無駄にすることにもなるので、事前にホームページやYouTubeを見てみてください。
さらに、メルマガを登録していただいて「こんなことをこの人は考えているんだ。」「そういう人間なんだ。」というところを見てもらった中で来ていただいた方が、お互いに話がスムーズにいくと思います。お客さんが本当に知りたいことを投げていただければ、それに対してためになるような回答をすることができます。ただ単に質問と答えを繰り返すだけでは、正直に言って意味がないと思います。
いい答えというのは、いい質問がないと得られないと思います。その人は本当は何を質問したかったのかを想像して、こんなことをしたいのかなと言うこともできますが、それが失礼になる場合もあります。そうなるとやっぱり、質問者さんがいい質問をするということが大前提なんじゃないのかと思います。
私が考える悪い質問とは、目的がよくわからないものです。インターネットでいろんなことを引っ張ってきて、何となくいっぱい質問することで満足しちゃうのは、ほぼ意味がないと思います。土地に関しても同じです。どんな土地が欲しいか、予算はいくらかという感じで、優先順位をちゃんと決めることが大事です。
まずは、おぼろげでもいいので、どんな家が欲しいかを考えてください。また、大きさはどのくらいか、どういうところを大事にしたいか、最終的にはここがいいかなという感じで考えて、質問を組み立てていくのがいいと思います。
“住宅選びは失敗すると、一生不自由な生活に耐えなければいけなくなる故に真剣に向き合うべきテーマだと思います。”とのことですが、これは難しいです。住宅業界の方でもそう思う人は少ないはずなので、一般消費者の方で本当にそう思うという人はかなり少ないでしょうね。
自分が作っている家に問題があるかどうかという意識はないと思います。何となく流れ作業で毎回同じようにやっているから、それに対してすごく疑問があるとか、本当はもっとこうやった方がいいと思っている職人さんはいないと思います。これは建売だからとか、大手ハウスメーカーだからとか、中小工務店だからというわけではありません。毎日普通に同じことをやっているだけなので、悪意があってわざわざこんなことをやっている人はいないと思います。
消費者の方は本当に千差万別じゃないですか。私が同じことを説明しても「そうなんですね。」と、ちゃんと聞いていただけるお客さんもいれば、同じ説明をしても、全く聞く気がないような人もいるわけです。でも、その人の興味の問題なので、仕方がないことだとは思います。
家が嫌だからといって、いきなりぶっ壊して路頭に迷うとか、ピョーンと引っこ抜くとか、そんなことはしません。寒い・暑いとか、窓が冬になるとすごく結露するとか、機械が壊れるというように、ボロボロと故障が出てくると、どんな消費者の方だって「何だかな。」と思うはずです。ただ、そこまで予想しろというのも難しいですよね。
感じる人は感じる。感じない人は全く感じない。この差は本当に大きいですが、結局はご本人様が納得するかどうかなので、こういう部分において、家づくりというのはなかなか難しいなという感じがします。いずれにしても、不味いお店の話から始まりましたが、意外に深い話になりました。