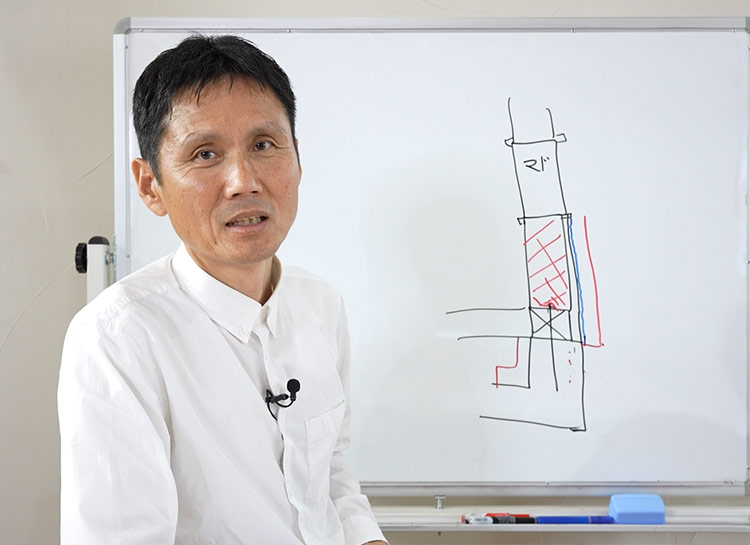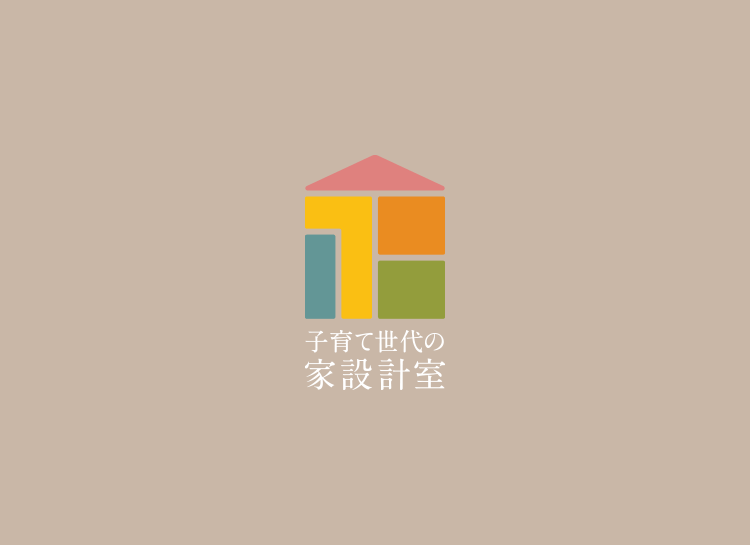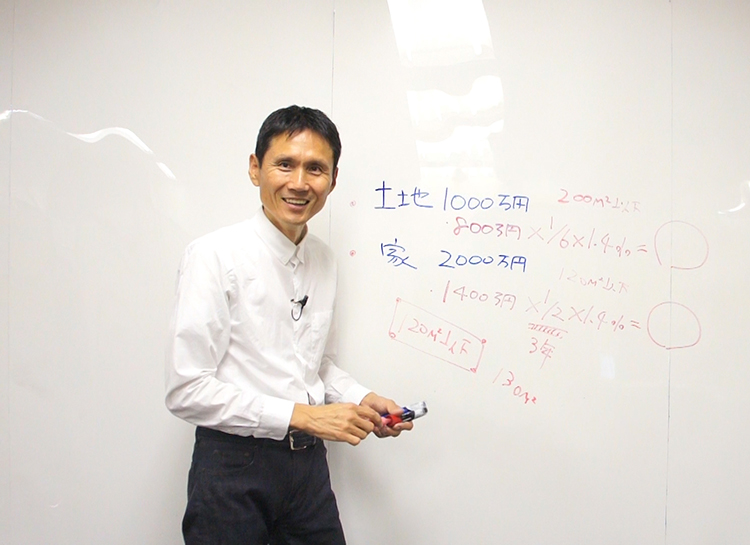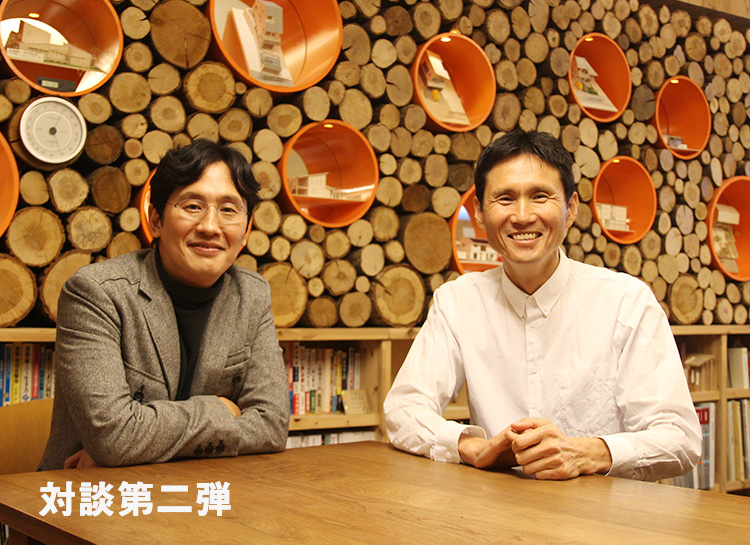https://youtu.be/l-xSPPP2Jlw
今回は、私のメルマガに対していただいた感想をみなさんと共にシェアしたいと思います。
まず最初の感想です。nobandさんからいただきました。
「お世話になります。個人的にはYouTubeで学ぶより、◯か×かの一覧表で判断したい人の方がたくさんいると思います。というか、最近は物価高も相まって、建築系YouTube離れさえ感じます。関心がお金に向いているというか。」
他の動画でお話しした某大手ハウスメーカーの広告は、平屋25坪でいくらと書いてあって、イメージ画像が続くんですが、途中から現実的な間取りが出てきて、最終的には別途工事がこれだけ必要だとか、蓄電池と太陽光は別で契約する必要があるということがわかります。それも1つの家づくりの方法なので、そういう会社がいいという方がいても全然構いません。また、わけのわからないことをぐだぐだ言っている私の会社に興味を持ってもらって、家づくりを依頼していただく方がいても、もちろん構いません。
ただ、前者は今の世の中の流れにものすごくマッチしていますが、10年後はどうかな?という感じはします。世の中の流れが変化する時に飛びついてしまうと、大体は違う方向に行ってしまうので、気をつけていただいた方がいいかと思います。
先月、当社のモデルハウスで、見学時間の最長記録を達成した方がいました。10時にいらっしゃって、お見送りをしたのが夕方5時10分だったので、7時間10分ずっといらっしゃったことになります。家の話も当然しましたが、7時間10分のうち、家の話は2時間くらいで、残りの5時間10分は趣味や仕事、人生の話をしていました。そのお施主さんは、私と同級生くらいの方でした。そこそこお金も貯まっているし、住んでいたマンションも高く売れそうだし、親も年を取ってきたので面倒を見なくちゃいけないということで、早期退職制度を利用して家を建てようと、急に思いついたそうです。たまたま私のYouTubeを発見してくれたのかもしれませんが、バーッと見て勉強して、「こういうのがいいんだ。」「これはダメなんだ。」という風に取捨選択していった結果、「地元の群馬県で建てるとなったら小暮さんに頼むしかない。」と確信したとのことでした。
その方と話をしてみて、勉強に時間は関係ないんだなと思いました。2〜3年勉強しても、勉強の仕方が悪ければ全く意味がありません。その方は半年間、私のYouTube以外にもいろんなものを見たり、私のメルマガを読んだりしてくれたんですが、取捨選択をバーッとしていって、「自分の家をこう作りたい。」「こういう生活をしたい。」ということを温めていった結果、それ以上勉強しても仕方がないと思ったみたいです。
勉強すればするほどいい家ができるというわけではありません。土地も全く同じです。一生に1度だからゆっくり探したいという気持ちもわかりますが、3〜4年探していい土地に巡り合えたというケースはなかなか稀だし、お金に余裕がある方じゃないと無理かなという感じがします。また、選ぶ際に一番重要なのは、優先順位を決めることです。さらにその中で、一生懸命選んだり探したりするしかありません。
若い方は知らないかもしれませんが、私は子どもの頃から「住めば都」という言葉をよく耳にしていました。例えば、土地を持っていない方が土地を探すことになったとします。実家の近くの土地は、田舎で不便だからそんなに人はいないけど、自分が昔過ごした場所ということで安心感があるし、どんな土地なのかは簡単に想像できますよね。そうなると、不便な田舎でもいい土地に見えてきます。でも、実家のない田舎の土地には住みたいと思わないはずなので、同じシチュエーションでも考え方によって変わることはあると思います。
夢も現実も大事ですが、勉強はすればするほどいいわけではないと思います。去年、そういうことを感じたお客さんがいました。その方は、明らかにいろんな勉強をし過ぎている感じがしました。もっと言うと、欲が多すぎて、比較している部分が明確ではありませんでした。
ご依頼いただくお客さんにとって、価格は当然重要ですよね。いくらでもいいという人はいないと思います。でも価格と同時に、こういう家じゃないと困るとか、建ててからお金がかかる家は勘弁という要望も出てくるはずです。あとは、寒い家、暑い家、電気代がかかる家も絶対に嫌だと思います。価格も大事だけど、これは嫌だと思うことも大事ですよね。
去年家を建てたお客さんから、「小暮さんだったら悪いことはしないと思う。」と言われました。悪いことというのは、誤魔化すとか、嘘を言うとか、間違った施工をするということです。UA値やC値、断熱材、床下エアコンや屋根裏エアコン、パッシブ設計などをきちんとやってくれると思える人を選ぶことが、信用に繋がるんじゃないかなと思います。
世の中にはこういう話をしても響かない人もいるため、なかなか難しいですが、結局は価値観なのかなという感じはします。今は本当に建築コストが上がっているし、YouTubeは◯×で選ぶ感じになっているので、そういうことを考える余裕はありません。住宅会社さんもそういう風に宣伝をして、誘導している感じがものすごくします。
Facebookでも「今は本当にコストが高くなっちゃって、いい家に住みたいという人が可哀想。」とか、「小さい家を作るのが、今風の住まい方だったり生き方になっている。」ということを言っている人がいました。だからといってでかい家を作ればいいわけではありませんが、無理してまで小さい家を建てることは、本当にいいことなのかな?と疑問に思います。
太田市に、東矢島町というところがあります。駅からはちょっと離れていますが、区画整理をして綺麗になりました。大きなショッピングセンターもできて、若者が住みやすい街になりました。それまで太田市は工業の街という感じで、そんなに人もいませんでしたが、建売住宅屋さんがバーッと土地を買ったことで、太田市でも建売がどんどん建ち始め、安く家が手に入れられるようになりました。
ただ、建売住宅屋さんは日当たりについては考えません。東西方向に長い土地は日当たりが良くて高いため、南北方向に長い土地に家を建てることになるので、西か東にしか日が当たらなくなってしまいます。それでも注文住宅を建てるよりは、明らかに安いです。
20年ぐらい経って、たまたまその近くに行ったので見てみたら、外壁がすごい状態になっていました。風が通らないというのもあって、劣化が酷かったです。買っちゃいけないと馬鹿にするわけじゃないですが、今は寿命が伸びていて、あと30年ぐらいは住むことになるのに、どんどん暗くて寒い家になっていってしまうような気がしました。
家の性能が良ければ暖房で熱損失を防ぎながら住むことはできるし、2階から日射取得をするというテクニックを使うこともできますが、20年以上前にはパッシブ設計なんていう言葉もなかったので、そういう家が普通に建てられていました。いずれにしても、時代の流れは怖いなという感じがします。
次も、nobandさんからいただいた感想です。
「お世話になります。付加断熱の良いところは、たしかに断熱性が上がることもありますが、やはり結露計算をした時に壁構成をゴニョゴニョ考えなくても露点に達しづらいところかと思います。施工のあそこが不味かった、ボルトの熱橋が少し残った、みたいな場合でも何とかなったりするかも。あとは金属素材の制振ダンパーも結露計算には入らないし、断熱欠損の考慮もないかもしれない。そういう場合にも多少の安心感が出るかなと。」
nobandさんの家は、日射取得がしづらい奥まった土地にあるのに、変に中庭をコの字型に作っちゃったから、付加断熱をすることでUA値を下げたとのことでした。そのおかげで床下エアコンで上手く空調ができているそうなので、やって正解ですよね。あくまでもnobandさんの家みたいなところで付加断熱をやるのは、いいことだと思います。
ただ、日射取得ができるところでわざわざ付加断熱をするのは、どうなのかな?と思ったりします。付加断熱をするのはいいんだけど、何で窓を小さくしちゃったの?と思うような家もあるし、日射取得を阻害するような家もあったりするので、そういうのは優先順位が違うかなと個人的には思います。
柱の幅は基本的に、幅3寸5分の105mmか、4寸の120mmというのがポピュラーです。断熱材の量はそれによって決まります。そんなに高性能じゃないグラスウールだけど、120mmでOKとする会社もあります。当社も昔はそうでしたが、その後120mmよりもいいグラスウールが販売されたので、今はこっちを使っています。105mmのグラスウールの方が120mmのものよりも高性能になったことで、柱が細くなった分、構造材は減りました。ただ、施工的には楽になりました。さすがにこの厚みでこれよりも高性能のものとなると、断熱材の価格が高くなってしまいます。
一応、内断熱が基本ですが、これでもまだ性能が足らない場合につけ加えるのが外付加断熱というものです。ただ、そもそも入っている断熱材のグレードをかなり低くして、セールスポイントを作るというケースも見られます。グラスウールの105mmとかを使えばいいんですが、袋入りの10Kなど、すごく性能が低いものを使うということです。トータルで言えばいいんじゃないかと思うかもしれませんが、実は反対側に使っている断熱材も厚みが30mmしかなかったりします。手間も増えるしコストも上がるけど、何となくすごそうに見えるわけです。
付加断熱では厚くすればするほど窓枠よりも飛び出しちゃうので、結局、窓枠周りの処理をするのにどんどんお金がかかることになります。付加断熱と言いながら、すごく薄いものが貼ってあることになるわけなので、どうなのかな?と思うところも正直あります。ただ、nobandさんが言ったように、付加断熱をすることによってゴチャゴチャ考えなくてもいいとか、金属の制振ダンパーは結露計算に入らないということもあります。たしかに外から塞いじゃうから、熱が入りにくいというのはありますが、そんなに影響はあるのかな?とは思います。
ちなみにnobandさんが「ボルトの熱橋が少し残った」と言っていましたが、貫通している金物ボルトにはほとんど熱橋の影響はありません。付加断熱をせず内断熱でも、冷えて地層に影響を及ぼすことはほぼありません。北海道だったらわかりませんが、5地域以降の場合ではほぼないし、結露もしないというのが定説です。
ボルトに発泡ウレタンを吹く人もいますが、西の巨匠曰く「あれは1つの宣伝かな。」とのことです。それをしても変わらないし、結露することもないそうです。ただ、当社の場合は一応吹いています。発泡ウレタンは基礎断熱でも使うので、どうしても余ってしまいます。また、1回蓋を開けると後からは使えません。なので、「余るんだったらついでに吹いとけ!」という感じで、大工さんに吹いてもらっています。決してあれがないと熱橋で結露して問題が起こるということはありません。
nobandさんからいいコメントをいただいて思いついたことがあったので、ミックスしてお話ししてみました。参考になれば幸いです。