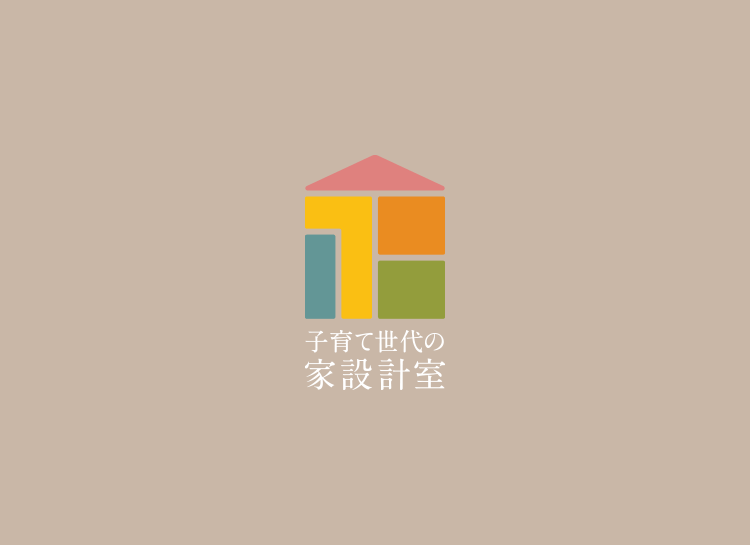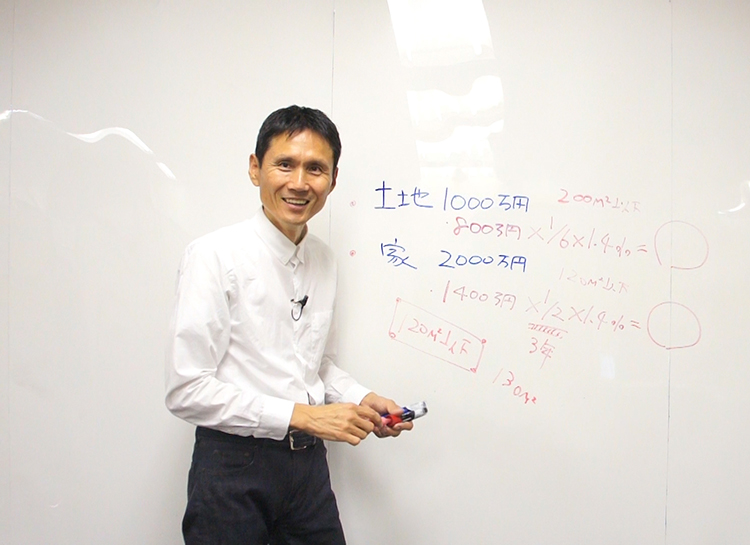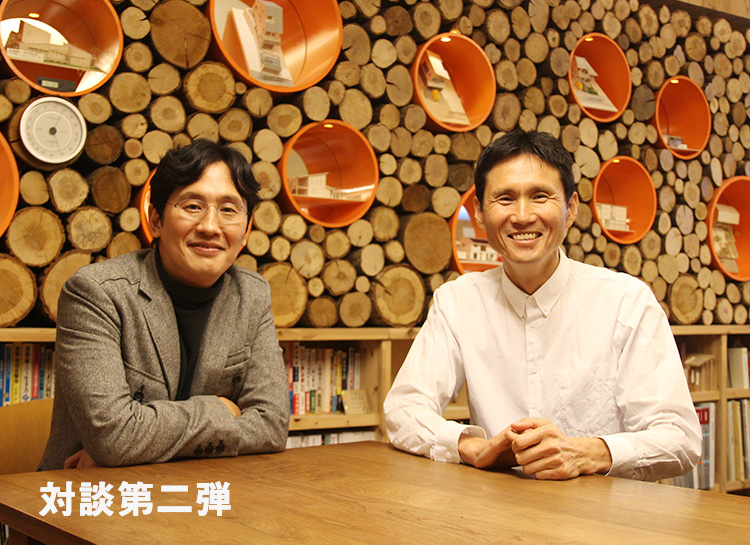今回は、私の配信したYouTubeに対するコメントをみなさんと共にシェアしたいと思います。
早速ですが、以下の動画に対するコメントをご紹介します。
◼︎正しい床断熱の施工方法
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/tadashii_yukadannetsu/
「いつも勉強させていただいております。床断熱で断熱材と合板の間の夏型結露リスクを教えてください。可変透湿気密シートを間に入れた場合、基礎内の湿気が合板で止まり、冷えた床の影響で結露しますでしょうか?また、断熱材と合板の間には通気層があるのでしょうか?ご教示ください。」
おそらくですが、壁の構成を床にするイメージでいられるのかなと思います。壁と床の最大の違いは、床下の空間があるかどうかです。壁というのは結局、外気に触れっぱなしじゃないですか。夏は熱気がバンバン放射されるし、冬であれば冷気がどんどん放射されるから、温度の変化が大きいわけです。屋根に関してはさらに温度の変化が激しいので、断熱材を入れる時は、まずは一番温度の変化が激しい天井をガードして、次に壁をガードするというのが原則です。
床というのは、床下というコンクリートのカプセルみたいなものがあり、一部が泥の中に埋まっています。なので基礎断熱の場合、床に関してはそんなに変化はないですし、床を高断熱にしなくても快適になったりします。地域によって変わりますが、私が施工している家であれば、基礎断熱をどんどん厚くしていってもあまり効果がなかったりします。
足元は快適じゃないと人間は寒く感じるので、そういう意味では床もちゃんとやる必要はあります。ただ、それには限界があるかなという感じがします。壁や屋根を増やすと、外気に対してどんどん抵抗力が強くなっていいですが、床というのはそもそも半分埋まっているという前提条件があるので、真夏でも床下の温度は23℃くらいまでしか上がらないし、冬であれば16℃くらいを維持することになります。そのため、床はそこまでしなくてもいいという考え方もあります。
断熱材については、力を入れるべき部分と、ここまででいいかなという部分があるので、それがわかっていないといけないと思います。例えば、この辺りで作るのに、基礎断熱の断熱材にすごいものを入れるとか、全面に敷いちゃうとか、中も外もやるとかして「うちの基礎断熱はすごいでしょ!」とアピールする人がいますが、「そこまでやってどうするの?」と思ってしまいます。計算上はたしかにすごいですが、それが室内に影響するかどうかはまた違う話になってくるので、こういうのも1つの経験値なのかなという感じがします。
別に好きだったら趣味としてやってもいいですし、お金がかかってもやりたいというのであればいいですが、やっても無駄かと思います。そんなお金があるんだったら、造作をするとか、外構をやるとか、いい椅子を買うとかした方がいいです。それでもお金が余っちゃうなら、家族で旅行をした方がいい気がします。
床断熱は、ベタ基礎が前提だと思います。絵のように、床の下地になる合板をペタッと貼ります。壁の内側には、フローリングや無垢の床を貼ります。合板というのは下地材です。断熱材は、空気が下に流れる状態になっているので、夏は暖かい湿気を帯びた空気が入って、冬は冷たい乾燥した空気が入ってしまいます。外に近い環境になってくるので、冷たい空気や暖かい空気が部屋の中に行かないようにしっかりと断熱をする必要があります。
いただいた質問への回答ですが、結論からすると夏型結露は起こらないと思います。床下は直射日光が当たっているわけじゃないので、外壁みたいな勢いでとんでもなく熱くなることはないからです。例えば、外壁の通気層が上手くいっていないのに暖められて、それと合わさったものが壁の断熱材の中に来てしまい、室内が暑くなってエアコンでガンガン冷やすとします。その結果、中の断熱材が結露を起こすのが夏型結露という現象です。だからといって、夏型結露が起こる可能性はゼロではありませんが、そこまでのシチュエーションはあまりないように思います。
逆に断熱材がなかったとしたら、もしかしたらベニヤの裏側に水滴がつくかもしれません。断熱材があれば、それをガードをするはずです。どんな断熱材を使うかにもよりますが、おそらく床断熱の場合で一番多いのは、発泡スチロール系のものだと思います。要は水を通さないものです。グラスウールを使う場合は、透湿防水シートなりを貼るのが原則です。基本的に透水防水シートというのは、外壁の中に雨水が入った時に水が流れるようにするためのものですが、それよりも、風の影響を受けないようにするために使うものだったりします。
断熱材というのは、そもそも中に空気の粒がいっぱい入っています。セルロースファイバーは紙、グラスウールはガラス繊維というのは、あくまでも使っている材料のことです。ガラス繊維だから暖かいわけではありません。セルロースファイバーも同じで、新聞紙を使って中に空気を入れているというだけであって、新聞紙が暖かいわけではありません。
絵のようにすると、断熱材の性能がなくなってしまうので、防風層を取り、断熱材の中に風が駆け巡らないようにするのというのは原則論です。特に床断熱をやる場合は、壁でも屋根でも同じです。ただ、通気層というのはあくまでも断熱材の外でやるものであって、中でやるものではありません。世の中には、壁の中に空気を通して湿気を防止する家もあるらしいです。その場合は発泡スチロール系の断熱材を使うんでしょうね。グラスウールや繊維系のものを使ったら、とんでもないことが起きてしまいます。
理論的なことを理解しながらやっていかないとおかしなことが起こったりするので、シンプルに、余計なことはしないのが一番です。断熱材はピタッとつけて外側に通気を回すとか、防風層を作るというのが原則かなと思います。これは床と壁の話ですが、屋根も全く同じです。屋根断熱の通気というのは、野地板の上で取っても下で取ってもいいですが、それについてはまた他の動画で解説しようかなと思います。
家というのは、なぜこうなのかとか、こういう理屈でこうなっているというのがわかってくると、よりシンプルになっていきます。変に勉強しすぎてしまうと、話が複雑になってしまいます。いずれにしても参考になれば幸いです。